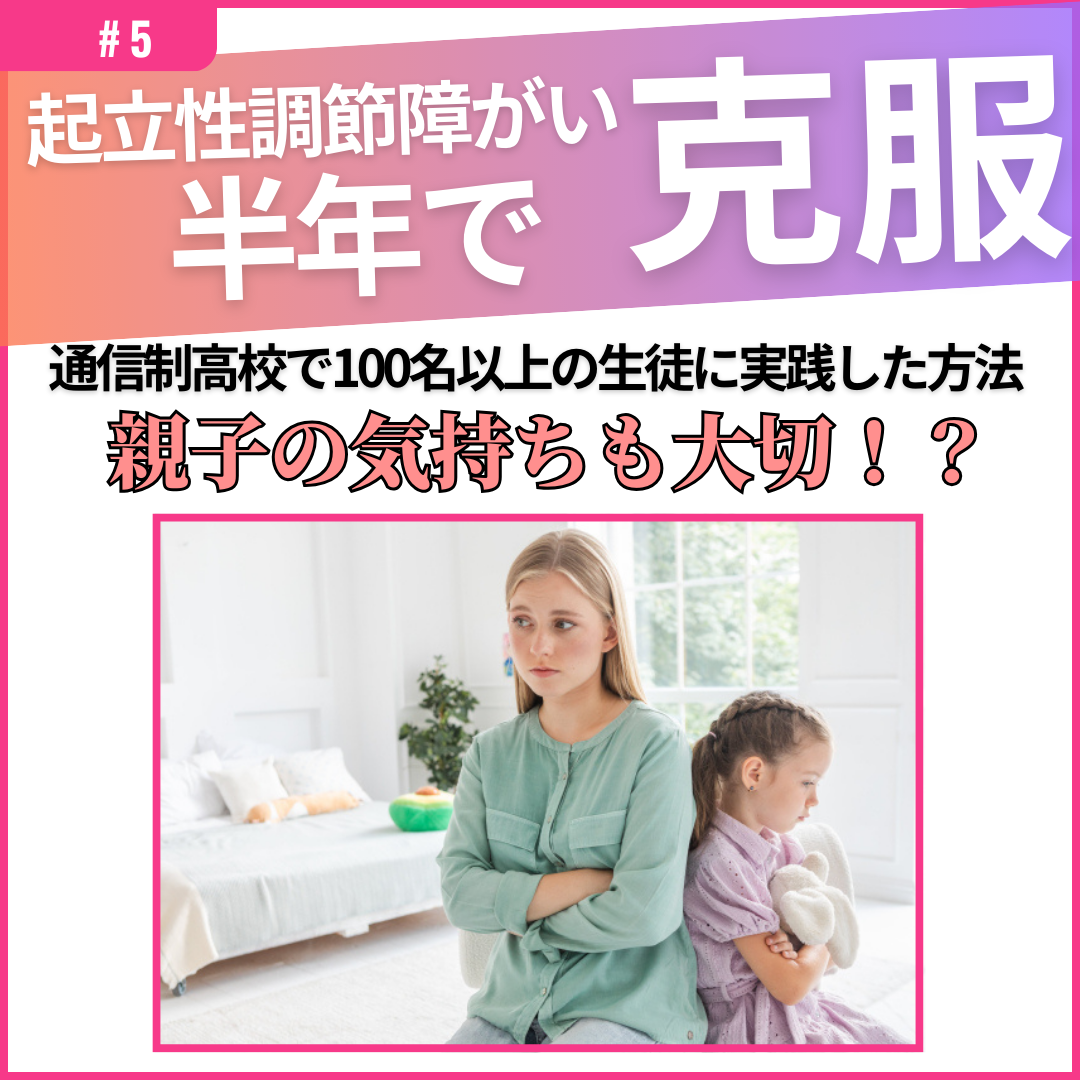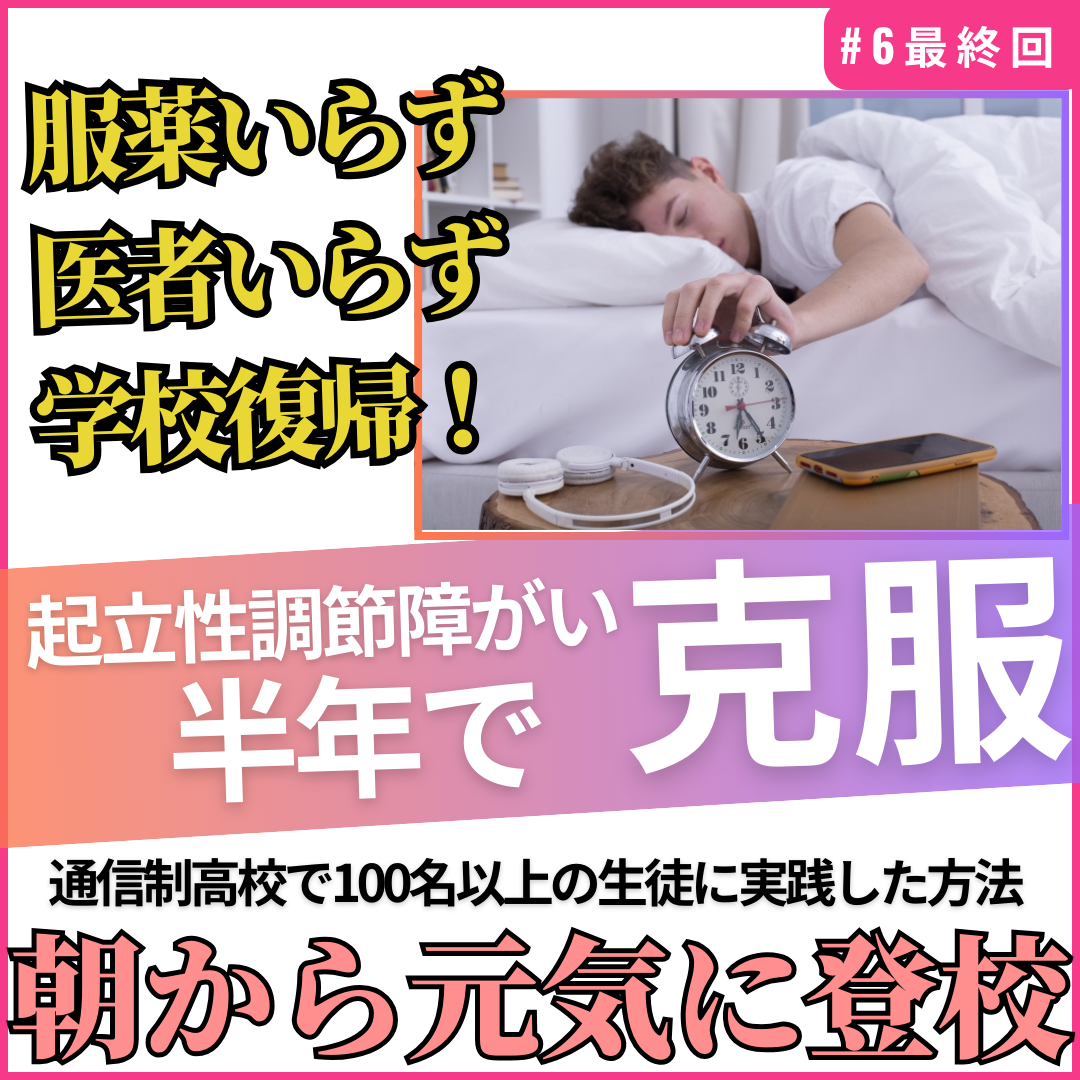起立性調節障害の回復には、生活リズムの調整や栄養管理だけでなく、気持ちの持ち方や生活環境の工夫も重要です。焦る気持ちや周囲からのプレッシャーをうまくコントロールしながら、自律神経を整えやすい環境を作ることで、よりスムーズな回復を目指せます。本記事では、起立性調節障害と向き合う親子の心構えや、環境を整える具体的な工夫について紹介します。

1. 気持ちを整えるための考え方
起立性調節障害の回復は一朝一夕ではなく、時間がかかるものです。そのため、焦りすぎず「今できること」を積み重ねることが大切です。
親子で意識したいポイント:
- 「昨日より今日、少し前進できたらOK」
・毎日100%を目指さず、「昨日より少し良くなればいい」と考える。
・たとえば「今日は決めた時間に起きられた」「朝食をとれた」など、小さな成功を積み重ねる。 - 「周りと比べない」
・他の子と同じようにできないことに落ち込まず、自分のペースを大切にする。
・家族の中でも「○○ちゃんはできるのに…」と比較しない。 - 「親も自分を責めない」
・子どもが思うように回復しないと「自分の対応が悪いのでは?」と親が自分を責めてしまうことも。
・でも、起立性調節障害は環境要因だけでなく、体の自律神経の働きによるもの。
・親も完璧を求めず、無理せず向き合うことが大切。

2. 環境を整える工夫
起立性調節障害の改善には、外的な環境も大きく影響します。特に、朝起きやすくするための工夫や、自律神経を整える環境づくりを意識しましょう。
朝スムーズに動き出せる環境を作る
- カーテンは遮光しすぎない
・朝の光が部屋に入ることで体内時計がリセットされ、自然に目覚めやすくなる
・遮光カーテンではなく、レースカーテンなどを活用。 - 目覚まし時計はやさしい音で
・突然大音量のアラームが鳴ると、交感神経が過剰に刺激され、起きるのが辛くなる。
・自然音や、徐々に音が大きくなるタイプの目覚ましを使用。 - 朝の準備をシンプルにする
・朝の動作を少なくするために、学校の持ち物を前日のうちに整理しておく。
・朝食は手軽に食べられるものを準備し、迷う時間を減らす。
・起きてから動きやすいように、必要なものをすぐ取れる場所に置いておく。

自律神経を整えやすい環境づくり
- 室温・湿度の調整
・部屋が寒すぎたり暑すぎたりすると、自律神経の働きが乱れやすい。
・冬は18〜22℃、夏は25℃前後を目安にエアコンや加湿器を活用。 - 騒音を減らす
・外の音や家の中の生活音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズを活用する。 - 夜のリラックスタイムを確保
・寝る前にスマホを控え、間接照明の部屋で過ごす。
・深呼吸やストレッチなど、寝る前のリラックス習慣を取り入れる。

3. 家族でできるサポートの工夫
家族の理解や協力も、起立性調節障害の改善には欠かせません。
プレッシャーをかけない声かけ
- NG例:
「早く起きなさい!」、「なんでこんなに寝てばかりいるの?」 - OK例:
「今日はどんな1日にしようか?」、「今は体を整える時間だね。少しずつ慣れていこうね。」
家族間のルールを作る
- 「朝起きられなかったとき、どう対応するか?」を家族で共有。
- 「学校に行けない日でも、決めた時間にリビングに出てくる」など、少しずつ外の生活と接点を持つルールを作る。

まとめ
起立性調節障害の改善には、「気持ち」と「環境」の両方を整えることが大切です。
- できることから少しずつ始める気持ちを持つ。
- 朝の光や室温調整など、環境を改善する。
- 家族のサポートを受けながら、焦らず向き合う。
次回の最終回では、「半年で回復を目指すエジソンメソッド」について詳しく紹介します!