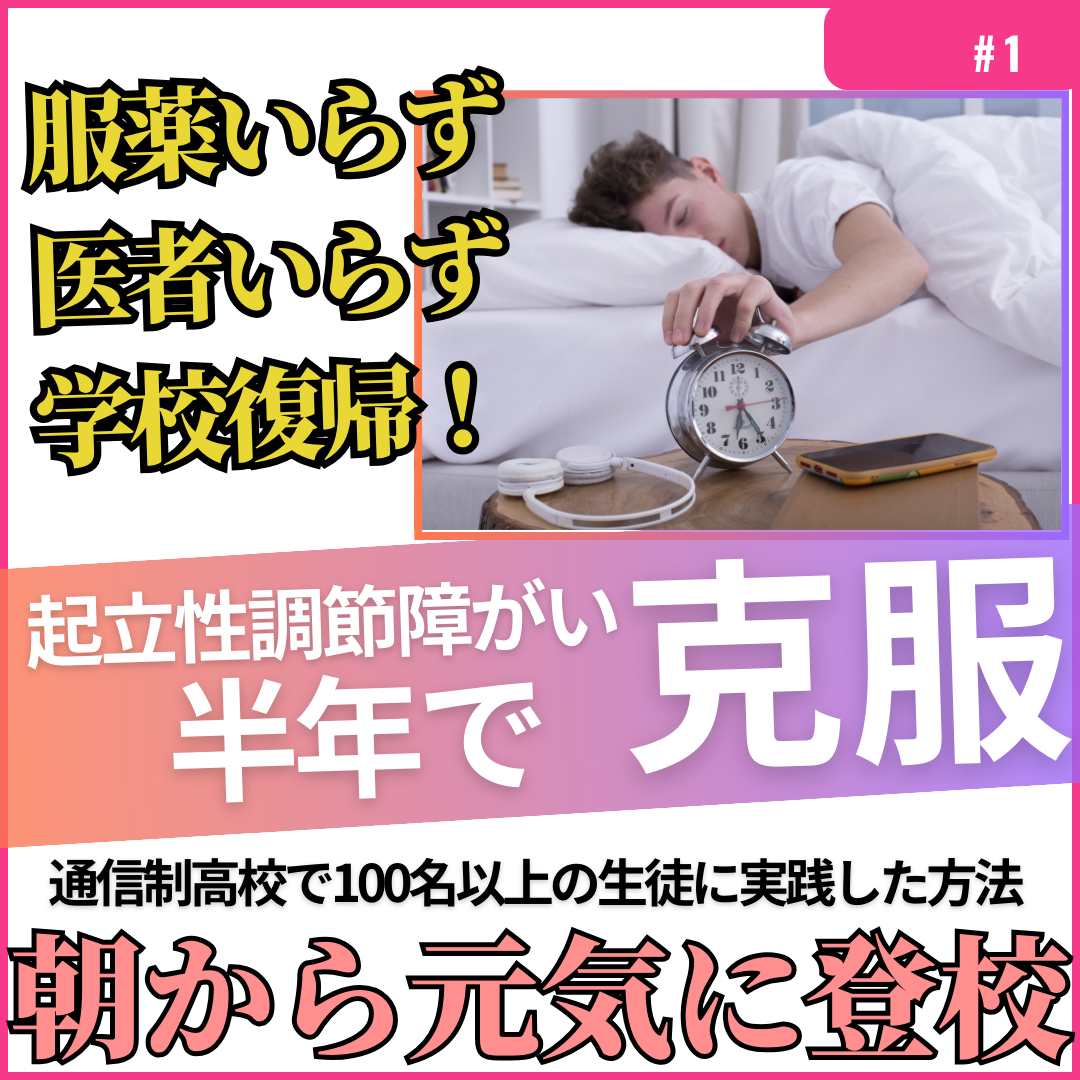起立性調節障害を克服するためには、生活リズムを整えることが重要な第一歩です。朝から夜までの習慣を見直し、自律神経を整えるための小さな工夫を取り入れることで、体調が徐々に改善していきます。本記事では、通信制高校で2,500名と向き合ってきて効果のあった、リズムを整えるための具体的な方法を解説します。
※「知っている」情報がほとんどだと思います。それを実行できるかできないかが実は回復への分岐点です。今なら無料個別カウンセリング受付中です。コチラまで。
1. 起きる時間を固定する
「早寝早起き」は一見理想的に聞こえますが、今のリズムから真逆な極端な早起きを強いることはかえって逆効果になることがあります。また早寝を強いることも同様です。「寝る」という行動は、「努力」で寝られるものではないのです。
方法
- 現在の起床時間からスタートし、不規則ではなく毎日同じ時間に起きることを目指します。
- 無理のない範囲で徐々に早める: 1週間ごとに起床時間を15分~30分ずつ早めていく。
- 起きたら、まずベッドの中でゆっくりと体を動かして準備をします。特に足を動かすのが効果的。詳しくは無料個別カウンセリング時に公開しています。
ポイント
- 親やサポート者と一緒に「最初の起床時間」を決めて共有しましょう。
- 起きる時間を守れたら、小さな達成感を一緒に喜びましょう。
2. 朝の光と体を温める習慣
自律神経を整えるためには、光と温度の活用が効果的です。
方法
- 光を浴びる: 起床の30分前にカーテンを少し開けておき、自然光や室内照明で徐々に明るくします。
- 体を温める: 起床直後に湯たんぽや毛布で体を温めることで、血流を促進します。下半身を動かすことも効果的。
- 白湯を飲む: 温かい白湯を飲むことで胃腸を目覚めさせ、リラックス効果を得られます。
ポイント
- 冬場や天気が悪い日は、適度に明るい照明を利用して光を補いましょう。
- 温かい飲み物には、白湯に加えてミチョ(美酢)を少量加えるのもおすすめです。
※あくまでも好みの参考まで。
3. 日中の光と運動の取り入れ方
日中に体を動かすことで、夜の快眠が促されます。
方法
- 外での活動: 徒歩や自転車など、無理のない範囲で外に出る習慣を作ります。
- 短い運動: 室内でもできるストレッチや軽い筋トレを1日10分から始めます。
- 光を意識する: 日中にできるだけ自然光を浴びるよう心がけます。
ポイント
- 無理をせず、「気持ち良い」と感じる程度に留めましょう。
- 運動後は、温かい飲み物でリラックスする時間を取り入れると良いです。
4. リズムを崩さない夜の過ごし方
夜の過ごし方次第で、翌朝の目覚めが大きく変わります。
方法
- 就寝前のスマホ制限: 就寝の1時間前にはスマホやゲームを終了し、リラックスできる環境を作ります。
- 入浴のタイミング: 夕食前そして就寝の2時間以上前にお風呂に入るのが理想です。
- 温冷浴を試す: 温かいお湯と冷たいシャワーを交互に使うことで、自律神経を切り替えるトレーニングができます。
ポイント
- 夕方以降のカフェイン摂取を控えましょう。
- 就寝時には足元をしっかり温め、足の裏は開放して体温調節をしやすくします。
まとめ
生活リズムを整えることは、起立性調節障害の克服に向けた重要なステップです。一度にすべてを取り入れる必要はなく、少しずつ無理のない範囲で始めましょう。次回の記事では、「腸内環境を整える栄養管理」について詳しくお伝えします。